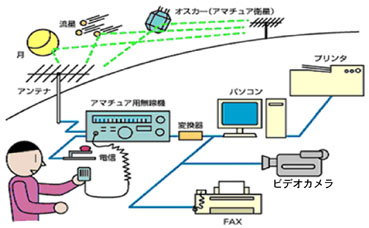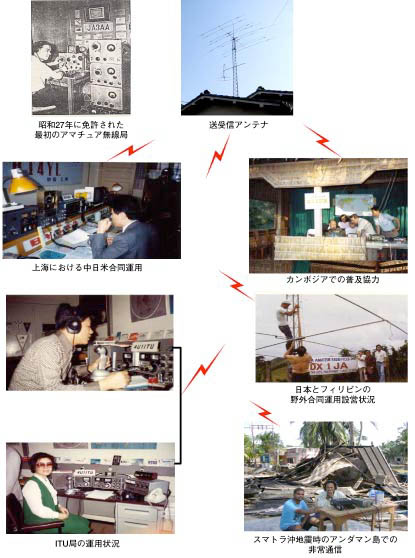| 明治34年 (1901) |
マルコーニが大西洋横断無線電信の実験に成功 |
| 大正元年 (1912) |
アメリカで無線法ができ、アマチュアの実験は1,500kHz以上の周波数が使用可能 |
| 大正14年 4月(1925) |
国際アマチュア無線連合(IARU)創立 |
| 大正15年 6月(1926) |
日本アマチュア無線連盟(JARL)設立(盟友37名) |
| 昭和 2年 9月(1927) |
草間貫吉(JXAX)が初のアマチュア無線局の免許を取得 |
| 昭和 4年 1月(1929) |
アマチュア無線の規定が確立され、呼出符号を付与 |
| 昭和 9年 3月(1934) |
函館大火で橋本数太郎(J7CB)により、わが国初のアマチュアによる非常通信実施 |
| 昭和16年12月(1941) |
太平洋戦争開戦と同時に私設実験局の運用禁止 |
| 昭和25年 6月(1950) |
電波法施行 |
| 昭和26年 6月(1951) |
第1回目のアマチュア無線技士従事者免許の国家試験実施 |
| 昭和27年 7月(1952) |
JA1AAを初めとする30名に予備免許がおりる、アマチュア無線再開 |
| 昭和33年 5月(1958) |
電信級及び電話級アマチュア無線技士の資格が新設 |
| 昭和34年12月(1959) |
JARL、社団法人として認可 |
| 昭和36年12月(1961) |
世界初の(米)アマチュア衛星「オスカー1号」打ち上げ成功 |
| 昭和45年 3月(1970) |
日本初の特別記念局(JA3XPO)が大阪万国博覧会で免許 |
| 昭和57年 3月(1982) |
レピータ局(アマチュア局の中継用無線局)の開設が認められ、JR1WAが免許 |
| 昭和57年 7月(1982) |
アマチュア無線技士の操作範囲が改正され、電信級、電話級の資格者にも画像通信、データ通信が許可 |
| 昭和61年 8月(1986) |
日本初のアマチュア衛星「ふじ」打ち上げ成功 |
| 平成 2年 2月(1990) |
アマチュア衛星「ふじ2号」打ち上げ。無線従事者の資格制度が改正され、電信級が3級、電話級が4級になる
|
| 平成 8年 4月(1996) |
2級〜4級アマチュア無線技士の操作できる空中線電力が引き上げられる |
| 平成 8年 8月(1996) |
アマチュア衛星「JAS-2」(日)打ち上げ成功 |
| 平成10年 5月(1998) |
アマチュア無線の公衆通信網への接続(フォーンパッチ)が許可制度導入 |
| 平成12年 3月(2000) |
国際宇宙ステーションのアマチュア無線局との通信に小・中学生の無資格操作が可能となる |
| 平成16年 2月(2004) |
アマチュア無線のデジタル通信方式(D-STAR)の運用開始 |