|
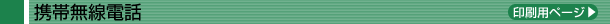
携帯無線電話は、日本では昭和54年に当時の日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)が開始した自動車無線電話サービスに端を発しています。
このシステムは、多数の基地局の無線ゾーンを蜂の巣の様に切れ目なくつなぎ合わせたサービスエリアを面的に構築し、この無線ゾーン内の移動体は、近くの基地局を介して公衆通信回線網内の加入電話、あるいは、他の移動体と接続して通信を行う仕組みになっています。
サービス開始当初の一つの基地局の無線ゾーンは、自動車が対象の通信であったため、直径約5~10kmの中ゾーンでした。しかし、その後技術の進歩により移動機は人間が携帯できるよう小型化、小電力化が図られた結果、無線ゾーンは約500m~1kmと小さくなり、現在のような携帯無線電話へと発展してきました。更に、需要に応じて無線ゾーンは、益々小さくなりマイクロセル、ピコセルへと発展しています。
略 史
昭和54年12月
(1979) |
日本電信電話公社(後のNTT)東京23区で自動車電話サービス開始
NTT方式(800MHz帯 25kHzアナログ方式) |
昭和60年 4月
(1985) |
電気通信自由化。NTT民営化及び電気通信事業者の新規参入可能となる。 |
昭和63年 5月
(1988)
12月 |
東京23区でNTT大容量方式の秘話サービス開始(狭帯域化)
日本移動通信(株)IDO(現KDDI)、東京23区でサービス開始 |
平成元年 7月
(1989)
9月 |
関西セルラー電話(株)(現KDDI)、サービス開始(800MHz帯 25kHz北米方式)
IDOが超小型携帯電話「ミニモ」を提供 |
平成 5年 2月
(1993) |
NTT DoCoMoが800MHz帯デジタル(PDC)方式の携帯・自動車電話サービス開始 |
平成 6年 4月
(1994)
12月 |
携帯無線電話端末売切り制導入
NTT DoCoMo、(株)東京デジタルホン、(株)ツーカーホン関西が1.5GHz帯デジタル携帯・自動車電話サービス開始
IDO(現KDDI)とセルラー各社でローミング・サービス開始 |
平成 7年 4月
(1995) |
関西セルラー電話(株)が800MHz帯デジタル携帯・自動車電話サービス開始 |
平成 8年 1月
(1996) |
(株)デジタルツーカー九州がサービス開始 |
平成10年 2月
(1998) |
セルラー各社(現KDDI)がCDMAサービス開始
NTT DoCoMoインターネット接続サービス開始 |
平成13年10月
(2001) |
第3世代携帯電話導入
W-CDMA、DS-CDMAの2方式、周波数は800MHz帯、2000MHz帯 |
|
(1)携帯無線電話システム回線構成図
携帯電話のシステムは、図のようにセルといわれる無線ゾーンを多数結合し、全体のサービスエリアを構成しています。
携帯電話、あるいは、加入電話からの通話は、交換局を介して接続して行われます。
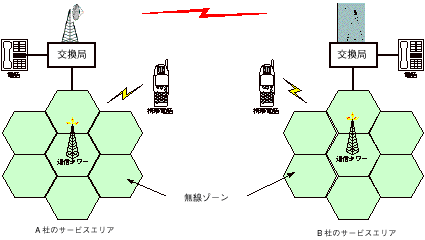
携帯電話システムの構成概要
(2)基地局設備の例
|
|
|
|
AUの基地局アンテナ
(KDDI提供)
|
|
NTTドコモの
基地局アンテナ
|
(3) 移動端末器
ア 第1世代自動車・携帯無線電話の移動機
① アナログ方式導入当初の移動機
自動車電話導入時の移動機大きさ等
1979年 6,000ml、7kg
1982年 1,500ml、2.4kg
1988年 500ml |
使用周波数帯 :925~940MHz(移動)
870~885MHz(基地)
チャネル数 :600
チャネル間隔:25kHz
空中線電力 :1W/5W
(移動機の受信入力の強さにより
発射電力を切り替える) |
|
② 携帯型移動機(ショルダフォン)
|
|
|
|
|
1986年
|
1988年
|
| |
|
|
|
ショルダフォンの運用
|
携帯が可能になったショルダフォン
大きさ : 500ml
空中線電力: 1W |
|
|
|
③ ハンディタイプの移動機
|
|
携帯型移動機の諸元
大きさ :150ml
方式名称 :NTT大容量方式
周波数帯 :925~940MHz(移動)
870~885MHz(基地)
チャネル数 :2,400
チャネル間隔:6.25kHz(インタリーブ)
空中線電力 :1W |
④ 平成3年頃の携帯電話の端末
イ 第2世代超小型携帯機
平成5年に第二世代のデジタル通信方式(PDC:Personal Digital Cellular)が導入されました。
PDCの通信方式の諸元は、次の通りです。
使用周波数帯 :800MHz帯、1.5GHz帯
アクセス方式 :TDMA/FDD
チャネル間隔 :50kHz(25kHzインタリーブ)
通信速度 :9600bps
移動機の大きさ:1,000ml
| |
○ 携帯電話の進化 |
| |
|
平成5年に導入されたデジタル通信方式の携帯電話は、平成7年にNTTドコモがデジタル方式の特徴を活かした[iモード]サービスを実施したのを皮切りに、EZ、写メール等、携帯電話からインターネットに接続してWebサイトが見られるサービスや、電子メールを送受信するといった携帯電話のインターネット端末が急激に進化しました。 |
|
ウ 第3世代デジタル方式携帯電話
平成13年に導入された第3世代の携帯電話方式は、ITU(国際電気通信連合)が作成した国際標準規格であるW-CDMAとDS-CDMAの2システムでサービスが開始されました。
第3世代の携帯電話の特徴は、伝送速度最大384kbpsのパケットサービスの他、インターネットから音楽、動画配信サービスを受けうことができる等、更に機能の進化を続けています。
第3世代の携帯電話の諸元は、次の様になっています。
| |
使用周波数帯は、800MHz帯、2GHz帯
チャネル間隔:
100kHz又は200kHz(DC-CDSMA)、
50kHz(MC-CDMA)
空中線電力 :0.25W以下 |
|
エ 移動機の容量の変化
移動機の容量は、技術の進歩に伴って小さくなっています。その推移を次のグラフに示しました。
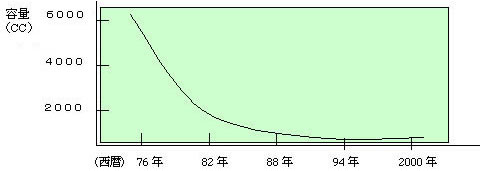
|
日本における、携帯電話・PHSの普及率
(総務省資料より作成)
|
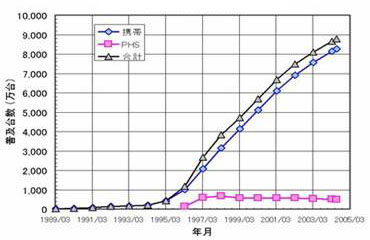 |
|